冬の香りいろいろ
冬に嗅げる香り![]()
イチョウの実は雌の木になる。


柚子の秘境を訪ねる
〜島根県益田市 美都町〜
秘境の柚子
島根県益田市から東へ、かつては秘境として人を寄せ付けない山間部に柚子畑が広がっています。5月の連休明けに開花し、11月に実ります。

美都町の柚子の出荷量は年間200㌧近く。25ヘクタールの農地で栽培されています。県内の和菓子店へ柚餅用、東京、大阪のレストランに出荷されています。出荷量では四国の各県や九州の大分や宮崎に比べ少ないものの、ゆったりとした傾斜地にのどかに栽培されているのが特徴。柚子に似合う最高のロケーションです。
 早朝、凛とした芳香を放つ。ミツバチよりも早く出逢いたい。
早朝、凛とした芳香を放つ。ミツバチよりも早く出逢いたい。
美都町の山間部に柚子畑が点在しています。
美都温泉を中心に道路が広がっていますから、ドライブするとすぐに見つかるでしょう。家々の庭にもほとんど柚子が植えられています。春の開花が一番香りを楽しめますが、秋の収穫期も黄色い色がとてもきれいで見応えがあるでしょう。

たわわに木に実をつける様は壮観です。
春は香りを、秋には果実を 5月上旬そろそろ開花
5月上旬そろそろ開花
平地では稲作を、傾斜地は柚子栽培に適しているようで、段々畑の柚子畑や、田んぼの脇、山間部のわずかな傾斜地に植えられています。
花の香りは5月中旬
開花が早い時期は連休の最中、通年は連休のあとあたりに開花します。開花期間は約一週間ほどです。1日中香りを楽しめますが、朝日が昇る頃がフレッシュな香りを堪能できます。昼頃は太陽が強く香りの揮発が活発なので過朝夕に比べてほんの少し弱くなっていますが充分楽しめます。
車で近くを走行していると窓から香りを感じ取れます。
 5月連休明けに開花
5月連休明けに開花
柚子畑では農家の方の挨拶と承諾を
柚子畑の感香は所有者に目的を告げてから楽しませて頂きましょう。農作業の邪魔をせず、繁忙期には立寄りを遠慮しましょう。
香りの楽しみは、傍目には不審者ぽくも見られがちなので、一言告げておくといいでしょう。
柑橘類は、花の香りが絶品。
5月の、開花時期には朝か夕暮れを狙って訪問すると強烈な香りの乱舞が楽しめます。あまりの香りに酔うかもしれません。心がすごいボリュームで平穏になってゆきます。日中も楽しめますが、朝か夕方以降は香りの量があふれんばかりなのでお勧めです。
五月の連休開けあたりの1週間くらいが嗅ぎ時です。美都温泉を中心に、周辺に柚子畑が点在しています。収穫期は、邪魔にならぬように注意して楽しみましょう。
 11月頃から完熟
11月頃から完熟
 収穫用に低く選定された樹形が美しい
収穫用に低く選定された樹形が美しい
柚子は捨てるところがない果実
柚子の最盛期頃、冬至の柚子風呂を楽しみましょう。柚子の果皮の裏側白い綿上の繊維はお肌をすべすべにしてくれます。お風呂の中で角質を擦るとしっとりとします。

香りのお土産
薬味の柑橘類では、とても人気の柚子です。収穫直後の「ヌーボー柚子」を秋の収穫時期は、安いものなら1個数十円ほどで売店で購入でき事もあります。皮も実も楽しめるのでジャム作り、生搾りして柚子酢、お風呂に浮かべたり、薬味や余ればポン酢づくりなどして楽しめます。
秋は、柚子の収穫
柚子ヌーボーを楽しむ。

柑橘系薬味のキングとでも言えそうな柚子は、香りの楽しみ方も豊富です。
ジャムやジュース、サイダー、柚子味噌をはじめ、ゆべしや菓子類など豊富です。地元の道の駅や温泉の売店などで入手できるので、楽しみましょう。
柴犬のルーツ「石号」の故郷
日本の柴犬のルーツとされている「石号」の故郷が同町二川です。昭和11年に石州犬研究室の調査で明らかになり、美都温泉に石号の碑が建立されています。近くに石号記念館もありますので、柴犬愛犬家には楽しみが多いです。
柚子感香の後は、温泉で仕上げ
柚子の最盛期なら柚子風呂が楽しめます。
 収穫時期は、毎週火曜日にゆず湯
収穫時期は、毎週火曜日にゆず湯
美都町の中心に美都温泉があります。アルカリ単純泉で少し濁った透明泉で肌がぬるっとして、よく暖まります。島根県でも有数の人気の高い温泉で掛け流し33度の良泉です。柚子の収穫期には、例年毎週火曜日にはゆず湯が提供されます。 立派な露天風呂もあり景色を楽しみながらゆったりと過ごせます。施設も浴槽もとてもきれいに管理されています。 傾斜地の柚子畑
傾斜地の柚子畑
近隣には、ペンションや、温泉宿があり静かな山間のひとときを楽しめます。
温泉横に道の駅があるので、情報週報に立ち寄るといいでしょう。柚子を使ったジュース「ゆずっこ」もおいしいです。
(記事中の写真は春に咲く花と、秋の実生の写真が掲載されています)
 美都温泉
美都温泉
美都温泉 湯元館
島根県益田市美都町宇津川ロ630-3
TEL.0856-52-2100
FAX.0856-52-3668
定休日:毎週水曜日
 美都温泉の売店で格安で売られている
美都温泉の売店で格安で売られている![]() 道の駅サンエイト美都
道の駅サンエイト美都
道の駅に隣接して美都温泉があります。

 レモン谷
レモン谷
瀬戸内レモンの島へ
〜広島県 生口(いくち)島瀬戸田〜
みかんに比べ栽培の歴史ま短く近代に栽培が始まったレモン。戦後西洋の豊かさの象徴として愛でられた存在。栽培が定着するまで幾多の苦難を乗り越えて根付いた国産レモン。
国内で栽培に成功したのは瀬戸内海沿岸と和歌山県。日本独自の品種改良のかいあって成功するも戦後のレモン輸入自由化の荒波で大半のレモン農家は転業を図らざるえなかった。 レモン谷から大三島を望む
レモン谷から大三島を望む
密かに無農薬自然栽培で苗木を引き継ぎ近年その品質に多くの一流料理人に認められるところとなり、一躍「瀬戸内レモン」のブランドとして脚光を浴び現在に至るドラマの果実です。そんな瀬戸内のレモンの代表格として出荷量も最もい多い広島県生口島に花の香りを求めを訪れました。
歴史あるレモン栽培の地 自然栽培の畑なら花と実が同時に楽しめる
自然栽培の畑なら花と実が同時に楽しめる
花の季節は5月中旬。温州や夏みかんなどの蜜柑類よりも若干遅い時期に開花します。花の香もさることながら無農薬レモンそのものは年中が収穫期です。枝に実った状態で1年ほどそのままで必要時にもぎ取り出荷するようです。なので花と実生を同時に見られるのも生口島の特徴。土産の生レモンや絶品レモンケーキ、ジェラート、レモン鍋など様々なレモングルメも揃っています。 レモンの花びらは少しシャープな感じ
レモンの花びらは少しシャープな感じ
レモンとアートの島
生口島は、尾道の南側に位置する島。西の日光と呼ばれる浄土真宗の耕三寺の島。古来より各地から耕三寺参拝で賑わう島であり寺は国の有形文化財として美しい佇まいを残しています。昔は船での参拝で賑わっていましたが、現在では広島県尾道市〜愛媛県今治市を繋ぐしまなみ海道上にあり、車で手軽に行けるようになっています。
かつての賑い感のある港町
島で一番賑わっている港を振出しに楽しむのがいいです。港から耕三寺への参道はしおまち商店街と称し贅を尽くした旅館ホテルや昭和の面影を残す店が旅の楽しみを膨らませてくれます。 世界第二位の長さを誇る斜張橋。手前が生口島
世界第二位の長さを誇る斜張橋。手前が生口島
参道を抜けると観光案内所、レンタサイクル、耕三寺、平山郁夫美術館があります。瀬戸内はアートで有名ですが、岡山県と香川県で開催されている瀬戸内国際芸術祭を起点に瀬戸内海各地でアートを取り入れた展示や建築などが豊富です。生口島でも随所に屋外アートの展示がされているので探し歩くのも楽しいです。 耕三寺
耕三寺
瀬戸田レモンと瀬戸内レモン
徳島県出身の米津玄師のLemonに歌われているように徳島のみならず四国各県でも栽培が行われています。瀬戸内地方の気象が柑橘栽培に適しているためです。「瀬戸田レモン」は生口島産で他の瀬戸内産は「瀬戸内レモン」と一般的に呼ばれています。菓子やドレッシングなどにもよく使われていますので表記をチェックすると楽しいです。
 平山郁夫美術館
平山郁夫美術館
レモン谷
生口島のなかでも風光明媚なレモン谷と呼ばれている地区は、生口島と大三島をつなぐ世界有数の長さを誇る斜張橋の袂の傾斜農地辺りに広がっています。 レモン谷
レモン谷
瀬戸内の名物でもある多島美を優美な橋を込みで楽しめるビューイングスポットでもあります。レモン畑の大半は島の南半分です。縦断道路もあるので効率よくポイントを探せます。できればレモン谷以外でも海とレモンの花の美しいポイントを探して楽しみましょう。

嗅ぎ時嗅ぎポイント
朝なら日の出とともに立ち込める絶品の新鮮なレモンの花の香りを堪能できます。夕暮れなら雰囲気たっぷりの大人な香りが楽しめるでしょう。もちろん昼間もシーズンには香りが充満しています。フェリーで生口島(瀬戸田港)に上陸する人なら高根島との海峡に差し掛かる手前からレモンの花の香りを感じ取れます。船の上での感香は格別でしょう。
サイクリング、ドライブでもアートも見ながら 瀬戸田サンセットビーチ
瀬戸田サンセットビーチ
車ならぜひ窓を全開にして島を探索してください。自転車なら島の南半分約12キロのコースで充分に堪能できます。オープンカーでの来訪なら格別。疲れたら島の北西部にあるロードサイドのジェラートショップがお勧めです。もちろんオーダーはレモンジェラート。
 ジェラートショップ
ジェラートショップ 花の香を堪能したらレモンジェラートと仕上げ
花の香を堪能したらレモンジェラートと仕上げ
 左生口島、右高根島
左生口島、右高根島
隣の高根島も蜜柑栽培
時間があれば橋でつながっている隣の高根島(こうね)はみかんの栽培が主なので、レモンの花の開花が遅いようならこの島で高根みかんの花の香りを楽しむといいでしょう。高根大橋かの眺めはお勧めです。ひょっとして平山郁夫の生家が見えるかも。
お土産も楽しい
 お土産の種類も豊富
お土産の種類も豊富
香りは持ち帰れませんが、お土産ならレモンの記憶を持ち帰れます。駅構内にも美味しいレモンケーキの店があったり、瀬戸田の観光案内所付近に瀬戸田の人気洋菓子店があります。耕三寺の門前にもあります。
ぜひ生のレモンもどうぞ。広島県のJAでは減農薬開花時期以降の農薬は使用していませんので県産の生レモンは皮ごと食べられます。
レモン農家さんは、レモンは実や果汁よりも皮をぜひ使ってくださいとのこと。果物店でもレモンレシピを教えてくれる店もあります。名物のレモン鍋にチャレンジしてみるのも楽しいです。

 お土産屋さんのレモンのレシピがかわいい
お土産屋さんのレモンのレシピがかわいい
 生口島行の船が出る尾道駅前桟橋
生口島行の船が出る尾道駅前桟橋 尾道駅前 生口島瀬戸田港行のフェリー
尾道駅前 生口島瀬戸田港行のフェリー

 瀬戸田観光案内所
瀬戸田観光案内所
瀬戸田観光案内所
広島県尾道市瀬戸田町沢200-5
☎0845-27-0051
9:00~17:00
生口島地図
生口島ガイドマップ
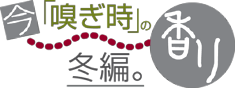
寒さこそ
最高の引き立て役
水仙の香りは冬の妖精の言葉
真冬のちょうど中心にいるような気持ちがしてくる
真冬の花の香三種(梅、山茶花、水仙)の中で、水仙は、梅が春の期待を感じさせる甘い香りとは異なり、あくまでも凛とした崇高な印象があります。
春を迎えるには、まだまだ早いですが、真冬を感じるにはうってつけの香りです。清々しく、さわやかな香りは、体内の汚れもきれいに流してくれるようなも感じます。
真冬のナチュラル・アロマテラピーに水仙郷を訪ねる旅はいかがでしょうか。
 紀伊水道に浮かぶ沼島を望む
紀伊水道に浮かぶ沼島を望む
 立姿が細腕のようだが力強い
立姿が細腕のようだが力強い
水仙の自生場所の多くは、風当たりの強い崖っぷちです。よりにもよって、厳しい環境を選ぶのか不思議です。だからこそ、水仙のあの凛とした男前な香りが誕生するのか、一度水仙に聞く機会があれば、教えてもらいたいものです。
 香りの強さが寒さを忘れる
香りの強さが寒さを忘れる
肌を切る風が育む真冬の絵巻
 黒岩水仙郷の入口
黒岩水仙郷の入口
淡路島の黒岩水仙郷は、房総半島、伊豆半島、越前海岸にならぶ水仙群落です。何れの地も寒風吹き荒ぶ場所ですが、香りる植物の少ない真冬の貴重な「嗅ぎ場」です。
開花は、概ね1月から2月頃までと比較的長い期間開花していますので、開花の知らせをチェックしながらお出かけ下さい。
漂着した球根を山に植えたのが始まり
急斜面に500万本の野生水仙が嗅ぎものです。
淡路島は、海峡と灘、湾に囲まれた日本神話にも登場する島です。かつて、日本に最初に漂着した香木もこの島です。そういう意味では、自然の貿易港なのかもしれませんが、香木も水仙も共に香り繋がりで少し不思議なものを感じます。
 へばりつくように咲き誇る。
へばりつくように咲き誇る。
 香りを堪能しながらの眺望は異次元
香りを堪能しながらの眺望は異次元
淡路島の南側に位置する黒岩水仙郷は、風と太陽が降り注ぐ急斜面にあります。かなり、人の手による管理がなされており、遊歩道も完備され子どもから大人まで楽しめます。
 一重咲きの野生ニホンスイセンが広がる
一重咲きの野生ニホンスイセンが広がる
斜面の頂上には展望スペースが有り、紀伊水道に浮かぶ沼島や、遠く和歌山や太平洋を望めます。風に当たりながら、水仙の語りかけるような香りをしばし聞いてみるのも、冬ならではの楽しみです。
*
黒岩水仙郷から少し76号線を東に行けば、立川水仙郷もありますので、時間が許せば併せてお楽しみ下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【追記】淡路島「黒岩水仙郷」最新情報
 2024年2月の時点
2024年2月の時点
黒岩水仙郷は2年間の閉園後、2023年12月のリニューアルオープン時にはカフェなど新設されが水仙畑の規模はほぼ半減していました。紀伊水道を望む優美な斜面は閉鎖され、東側駐車場あるの内陸部の谷斜面のみとなっていました。近隣に居住なら訪れてもいいでしょうが個人的には遠方より訪れる価値は感じれれませんでした。
淡路島水仙の丘 (3月中旬〜下旬頃開花)

近隣にあった立川水仙郷は2023年9月に閉園。代わって別の民間の水仙園が開園しています。黄色いラッパ水仙が大半です。香りはほとんどしないです。
兵庫県淡路市多賀369−9
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ローズガーデンは、
天然のアロマテラピー
究極のアロマ浴でリフレッシュ
バラを眺めながら、香りで満たされる
秋咲きのバラをたっぷりと味わいに出かけませんか。お部屋の中のアロマテラピーも気持ちいいですが、ビジュアルも楽しめるローズガーデンでの天然100%のアロマテラピーは格別です。
 伊丹市 荒牧バラ園
伊丹市 荒牧バラ園
ローズガーデン浴にはハーブテーをポット持参で
ローズガーデンは、各地にあります。バラ専門の庭園もありますが、植物園や遊園地の一角に整備されていたりします。温かいお茶とベンチに敷くハイキング用のざぶとん持参でゆくと、ゆっくりできます。
 大阪千里 万博公園バラ園
大阪千里 万博公園バラ園
植物園、ハーブ園の一角にあります
ちなみに関西なら大阪千里の万博公園をはじめ、ユニバーサルスタジオ、枚方パーク、宝塚ガーデンフィールズ、須磨離宮公園、布引きハーブ園、伊丹の荒牧バラ公園、浜寺公園バラ庭園、中の島公園バラ園、靱公園バラ園などがあります。
 大阪市 中之島公園 バラ園
大阪市 中之島公園 バラ園
近くのローズガーデンを探す。
大きなバラ園も種類が豊富でいいですが、量に圧倒されるので、こぢんまりしたバラ園などお勧めです。
ローズガーデンのベストシーズン
春と秋です。春咲き、秋咲き以外に四季咲きのバラもありますが、季節のいい春秋が種類も豊富でたっぷり楽しめます。
秋は、身近なバラ園にでかけよう
特に、秋咲きのバラは香りが春に比べて強く感じる事が多いです。春咲きに比べると秋のバラは小ぶりで花数も少ないと言われていますが、写真をご覧頂いても分かるように、充分に楽しめます。
 伊丹市 荒牧バラ園
伊丹市 荒牧バラ園
まずは、近くのローズガーデンを探してみましょう。Netや友達情報やタウン誌などでお気に入りが見つかったらタイミングを見計らって訪問しましょう。
ローズガーデンごとに代表的なローズがあります
それぞれのローズガーデンごとに、特に大切に育てているローズがあります。希少種や貴重種などです。大阪の浜寺公園には、アンネフランクが育てていたバラの種を改良しアンネの父に捧げたローズがあります。とてもきれいです。他にも代表種がありますので、お目当てに出向いてください。
ベストシーズン
時期は春なら5月〜6月。秋なら10月〜11月あたりです。気候や地域によって異なりますので事前にチェックして下さい。
 浜寺公園バラ園
浜寺公園バラ園

お気に入りの香りを探す
色と香りの関係?
最も香りが立つ時間帯は朝夕です。できれば太陽が昇る直後辺りが濃厚な香りを楽しめます。または、日没頃も香りを楽しめます。
 嗅ぎPointも探そう
嗅ぎPointも探そう
すべての花を嗅ぎ回ると傍目にも美しくありませんし、なにより鼻が疲れてしまいます。朝夕は、嗅覚も優位な時間帯ですので早めか遅めに訪れるのがいいでしょう。
 ナエマ
ナエマ
白系のバラはよく香る
香りのよく立つバラは、白系のが多いようです。花の近くに寄れば香りが飛び込んできますので「一目ぼれ」感性を全開にして探してみましょう。
 アスピリンローズ
アスピリンローズ
気に入ったバラに出会えれば、写真を撮るか、スケッチをして名前も記録しておきましょう。あわせて香りの印象を記録しておくと楽しいです。
 大阪市 中之島公園 バラ園
大阪市 中之島公園 バラ園
白系の花は相対的に香りが立つものが多いです。花の近くに寄れば香りが飛び込んできますので「一目ぼれ」感性を全開にして探してみましょう。
気に入ったバラに出会えれば、写真を撮るか、スケッチをして名前も記録しておきましょう。
ワイン好きの人が味わいの記録をとるように。
アロマテラピーに使用するローズ精油の産地は、ブルガリアやモロッコ、グラース産が有名です。園芸種と異なり小ぶりのダマスクローズやローズ・ド・メイや原種に近いバラの花です。
 野いばら(テリハノイバラ)
野いばら(テリハノイバラ)
それらのルーツが日本の野いばらと言われていますので、ローズガーデンに訪れたら、野いばらをチェックしてください。原種は香りも濃厚です。
 USJ Roses of Fame
USJ Roses of Fame![]() Universal Studio Japan「Ros
Universal Studio Japan「Ros
「Roses of Fame」
名前の由来が深〜い
バラの名前は、歴史的な名前がついたものや、イメージから命名されたもの、品種改良に関わった人の名前など由来やドラマがあります。
 アンネフランクのバラ
アンネフランクのバラ
お気に入りのローズの物語を調べてみると楽しみが広がります。
「香りのネ、」サイトは、嗅覚を開き豊かな感性を育むことを応援しています。
香りを楽しむ「感香旅行」のすすめ、鼻を使った遊びや暮らしなど、嗅ぐ事に焦点を当てた提案を行っています。嗅感覚を開く事で、五感全体が活性化します。「香りのネ、」の「ネ」は、フランス語で「鼻」の意味です。花など香りと、それらを嗅ぐ方の鼻、両方をまとめた造語です。(運営:香りの環境研究所)![]()
咽が渇いている時
どれを選びますか?
3つのコップには、無色透明の液体が入っています。
嗅覚無しで、安全性を推量る事は困難です。
無意識に、人は食品や環境の安全を嗅覚も全開でチェックしてます。
香りと嗅覚の関係
幼児期に豊富な「香りの原体験」を!
嗅感覚を育む機会を意識しましょう。
嗅覚体験は、バランス感性と受容能力を高め
生きる力を育みます。
特に、幼児期における生活基本臭や固有の暮し臭、自然界の香りとの出会いが、香りのボキャブラリーを豊富に蓄え、身体育成の礎となるでしょう。
音の名前(ドレミ)や、色の名前を覚えたように、香りの名前も覚え「絶対嗅覚」を養いましょう。加えて嗅覚刺激は、他の感覚器官の働きを活性化させます。情報収集の基軸となります。「鼻が利く」とは、感度がいい人の比喩で使われている事からも納得が行きます。
まずは公園で「香りの散歩」デビュー
深く知るなら「嗅覚教育」へ
旅行読売 寄稿(外部リンク)
「香り」で広がる旅の可能性
 どんな香りがするか嗅いでみよう
どんな香りがするか嗅いでみよう 人工香料に出会う前に自然香の体験を!
人工香料に出会う前に自然香の体験を!
香りに包まれに出かけませんか?
 ハナニラ
ハナニラ
見る観光にとあわせて、香りも感じる「感香」旅行のご案内。
香りのある時期は短いです、それだけに貴重な体験に加えて、感性を育むよりよい機会です。季節、場所毎に異なる香り体験が、日本では数多くの機会があります。
当「香りのネ、」サイトは「嗅ぐ」についての身体感覚をテーマに、嗅感覚の復権を提唱する香りの環境研究所のコンテンツです。
香りの散歩、感香旅行、日々香りに触れる楽しさ、あそび、嗅覚教育コンテンツなど公開しています。
主宰者:成瀬守弘 制作協力:Peppermint Studio

 TOP
TOP

















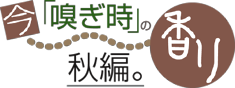































































































































 No Scent No Life
No Scent No Life




 HOME
HOME 前のページ
前のページ